ロブスターやザリガニは、レストランや家庭の食卓で目にすることも多い海産・淡水の生き物です。しかし、見た目が似ているため「どちらがロブスター?」「食べたことがあるのはどっち?」と混乱してしまう方も少なくありません。名前や種類、味や調理法まで知っておくことで、食事の幅が広がり、選ぶ楽しさも増します。
本記事では、ロブスターとザリガニの違いを分かりやすく丁寧に解説します。それぞれの代表的な種類や特徴、生態や生活環境、食卓での楽しみ方まで幅広くご紹介します。身近な疑問を解消しながら、食の知識も深めてみましょう。
ロブスターとザリガニの違いをわかりやすく解説

ロブスターとザリガニは、見た目が似ているだけでなく、呼び名や食べ方も混同されがちです。ここでは生物学的な分類や生息地、見分け方など、違いを分かりやすくまとめました。
ロブスターとザリガニの生物学的な分類
ロブスターとザリガニは、どちらも「甲殻類」に含まれますが、細かい分類では異なります。ロブスターは「エビ目・アカザエビ科」に属しており、主に海に生息します。一方、ザリガニは「エビ目・アメリカザリガニ科」や「エビ目・カワリザリガニ科」などに分かれ、淡水の川や池に住んでいるのが特徴です。
このように、同じ甲殻類でも分類が異なることから、生態や生息地、体の特徴にも違いが現れています。混乱しがちですが、分類を知ることでそれぞれの違いがより明確になります。
生息地の違いとそれぞれの特徴
ロブスターは、主に海洋に生息し、特に北大西洋などの冷たい海域でよく見られます。水深のある岩礁地帯や海底に棲み、夜行性であるため、昼間は岩陰や穴に隠れることが多いです。体が大きく、長いハサミを持つのが特徴です。
一方、ザリガニは淡水域に生息し、池や川、沼などでよく見かけます。比較的浅くて流れが穏やかな場所を好みます。種類によっては都市部の用水路でも生息しています。ロブスターよりもサイズが小さく、カラフルな種類も多いです。
見た目やサイズで見分けるポイント
ロブスターとザリガニを見分けるポイントはいくつかあります。まず、ロブスターは体長が30cm~50cm程度と大きく、ハサミが太くてボリュームがあります。体色は青緑や茶色が主流です。
ザリガニは体長10cm前後のものが多く、全体的に小柄な印象です。ハサミも細長く、体色は赤や黒、青などバリエーションがあります。下記に違いを表にまとめました。
| 特徴 | ロブスター | ザリガニ |
|---|---|---|
| 主な体長 | 30~50cm | 10cm前後 |
| ハサミ | 太くて大きい | 細長い、小ぶり |
| 主な色 | 青緑・茶色 | 赤・黒・青など |
食用としての利用方法と味わい
ロブスターは、高級食材として世界各地で楽しまれています。肉厚でプリプリとした食感があり、甘みのある風味が特徴です。蒸し料理やグリル、スープ、パスタなど、調理法も豊富で、祝いの席や特別な日の料理によく使われます。
ザリガニは、特に北欧や中国で食材として重宝されています。味はあっさりとしており、ロブスターよりもやや淡白な印象です。塩ゆでや炒め物、スパイス煮込みなどが一般的な調理法です。ザリガニ料理は、家庭料理からビールに合うおつまみまで幅広く親しまれています。
日本での呼び名や混同しやすい種類
日本では、ロブスターを「オマール海老」と呼ぶこともありますが、伊勢海老やザリガニと混同されることが少なくありません。特に、伊勢海老は日本固有の高級食材であり、ロブスターと混同してしまう方も多いです。
また、ザリガニについても「アメリカザリガニ」と「日本ザリガニ」といった異なる種類が存在します。呼び方や分類の違いを知っておくと、混乱を避けやすくなります。
本場イタリアで人気No.1!
3人に1人が選ぶパスタであなたの家もレストランに。
それぞれの代表的な種類と特徴

ロブスターやザリガニには、さまざまな種類が存在します。ここでは代表的な種類ごとに、特徴や違いをわかりやすく比較していきます。
アメリカンロブスターとヨーロピアンロブスター
ロブスターの中でも特に有名なのが「アメリカンロブスター」と「ヨーロピアンロブスター」です。アメリカンロブスター(Homarus americanus)は主に北大西洋沿岸、アメリカやカナダで水揚げされます。体が大きく、肉厚でジューシーな身が特徴です。
一方、ヨーロピアンロブスター(Homarus gammarus)はヨーロッパ周辺の海域に生息しており、アメリカンロブスターよりやや小型ですが、味は濃厚で繊細な甘みが感じられます。見た目でもアメリカンロブスターは茶色や緑がかった色合い、ヨーロピアンロブスターは青みが強い体色を持つ傾向があります。
日本のザリガニとアメリカザリガニの違い
日本のザリガニには「日本ザリガニ」と「アメリカザリガニ」が存在します。日本ザリガニは主に北海道から中部地方にかけて生息し、体長が5~7cmと小さめです。体色は黒褐色で、冷たい清流を好むのが特徴です。
アメリカザリガニは体長約10cmとやや大きく、赤色が鮮やかです。1930年代に日本に持ち込まれ、全国に広がりました。水田や池など身近な水辺でもよく見かけます。下記の表で主な違いをまとめました。
| 種類 | 主な体長 | 体色 |
|---|---|---|
| 日本ザリガニ | 5~7cm | 黒褐色 |
| アメリカザリガニ | 10cm | 赤色 |
オマール海老とロブスターの関係
「オマール海老」という名前を聞いたことがある方は多いかもしれません。オマール海老は、フランス語で表現されるロブスターのことです。特に「オマール・ブルー」はヨーロピアンロブスターを指し、「オマール・ノルマンディ」はアメリカンロブスターを指すこともあります。
日本では、洋食レストランやフレンチで「オマール海老」と記載されることが多いですが、実際にはロブスターと同じ種類です。料理名や産地表示によって呼び方が異なるため、混同しやすいポイントとなっています。
伊勢海老とロブスター ザリガニの違い
伊勢海老は日本の高級食材であり、祝い事などで重宝されています。外見がロブスターに似ていますが、実は別の系統です。伊勢海老は「イセエビ科」に属し、大きなハサミではなく長い触角を持つのが特徴です。
ロブスターは大きなハサミ、ザリガニは淡水に生息と、それぞれ違いがあります。伊勢海老は主に日本や台湾で獲れるのに対し、ロブスターは欧米中心に流通しています。
体の構造や色のバリエーション
ロブスターは、体が硬い殻で覆われており、特に大きなハサミが目立ちます。色は青緑や茶色、まれに青やオレンジなどの個体もいます。ゆでると赤くなるのが特徴です。
ザリガニは体が小型で、足やハサミが細長い傾向があります。色は赤や黒、青、白などカラフルです。体の色は住む環境や種類によってさまざまで、観賞用として飼育されることもあります。
ロブスターやザリガニの生態と生活環境
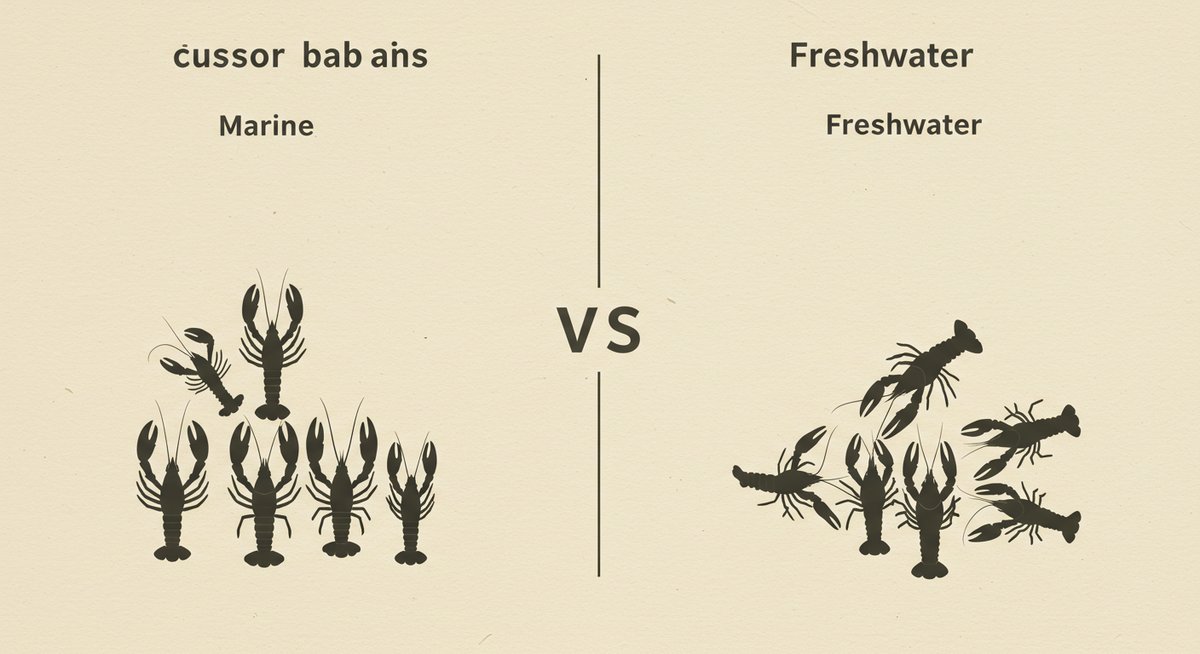
ロブスターとザリガニは、それぞれ異なる環境で独自の生態を持っています。生息地や行動、自然界や飼育環境での違いについてまとめます。
ロブスターの主な生息地と生態
ロブスターは主に寒冷な海域の海底に住みます。岩場や砂地のすき間に隠れて生活し、夜になると餌を探しに出かけます。主な餌は貝類や小魚、海藻などです。
長寿な個体も多く、20年以上生きることも珍しくありません。脱皮を繰り返しながら成長し、成熟したロブスターは繁殖のために移動することもあります。
ザリガニが暮らす淡水環境
ザリガニは川や池、沼などの淡水域に生息します。流れの緩やかなところや隠れ家となる石や水草が多い場所を好みます。雑食性で、水生昆虫や植物の葉っぱ、小さな動物などを食べています。
また、ザリガニは環境の変化に強く、水質が悪化した場所でも生きのびることができます。そのため、外来種として増えすぎてしまうケースもあります。
ロブスターとザリガニの行動や習性
ロブスターは夜行性で、暗くなると活発に活動します。大きなハサミを使って餌を捕まえたり、縄張りを守ったりします。脱皮によって体を大きくし、成長を遂げます。
ザリガニも夜間に活動が盛んになりますが、日中でも石の下や泥の中にじっとしていることが多いです。天敵から身を守るため、穴を掘って暮らすこともあります。繁殖期になると、オスとメスがペアになり、卵を守る行動も見られます。
野生下と飼育下での特徴の違い
ロブスターは野生では広い海底を移動し、自然の餌を食べています。一方、飼育される場合は水槽内でエサが与えられ、動きも制限されます。飼育下では脱皮や成長に注意が必要です。
ザリガニも同様に、野生では多様な環境に適応しながら生活しています。飼育下ではスペースや水質管理、エサのバランスが重要です。観賞用に改良されたカラフルなザリガニも多く見られます。
環境への影響や外来種としての問題
ロブスターは主に自然環境に大きな影響を与えることは少ないですが、乱獲による資源の減少が懸念されています。持続可能な漁業管理が求められています。
ザリガニは特に外来種問題が深刻です。アメリカザリガニが日本や他国に広がり、在来種や水生植物、農作物に悪影響を及ぼすことが指摘されています。生態系への影響を考え、注意深い取り扱いが必要です。
ロブスターとザリガニを楽しむための知識

ロブスターやザリガニをより美味しく楽しむためには、調理法や選び方、価格、歴史的背景などの知識が役立ちます。食卓を豊かにするヒントをご紹介します。
おすすめの調理法やレシピ
ロブスターは、蒸し料理やオーブン焼き、パスタのソースとして使うのがおすすめです。殻ごと調理すると、旨味が凝縮されます。バターやガーリックとの相性も抜群です。
ザリガニは、塩ゆでやスパイス煮込み、炒め物などが人気です。北欧ではディルとともに茹でる「ザリガニ・パーティー」の文化があります。日本でも唐揚げや味噌汁など、手軽な家庭料理として楽しむことができます。
市場やスーパーでの選び方
ロブスターは、生きたまま販売されていることが多く、動きが活発な個体を選ぶと鮮度が良い証拠です。殻に光沢があり、重みを感じるものを選びましょう。
ザリガニは、日本ではペットショップのほか、一部のスーパーや専門店で手に入ります。体色が鮮やかで、元気に動く個体が新鮮です。食用の場合は、衛生管理がしっかりしている店舗を利用すると安心です。
価格や流通の違い
ロブスターは高級食材とされ、特に大型のものは高値で取引されます。輸入品が多く、季節やサイズによって価格が変動します。冷凍製品も多く流通しています。
ザリガニは比較的安価で流通しやすい食材です。日本国内では主に観賞用ですが、近年は食用としての需要も増えています。生体や調理済みのものが販売されています。
ギフトやイベントでの活用
ロブスターは、贈答品やパーティー、記念日の特別な料理として選ばれることが多いです。鮮やかな見た目と豪華な印象が喜ばれます。ホームパーティーや家族の集まりにもおすすめです。
ザリガニは、北欧などで夏の風物詩として「ザリガニパーティー」が開かれます。日本でもイベントや子ども向けの体験教室などで人気です。家庭での集まりやアウトドアでも手軽に楽しめます。
文化や歴史にまつわるトリビア
ロブスターは古くからヨーロッパやアメリカで食文化の一部とされてきました。かつては貧しい人々の食事でしたが、現在では高級食材としての地位を確立しています。
ザリガニは、北欧の夏の風物詩や、中国料理の一品として親しまれています。また、日本でも子どもの遊びや生態観察の対象として身近な存在です。それぞれの地域で異なる文化や歴史が根付いている点も面白い特徴です。
まとめ:ロブスターとザリガニの違いを知れば食卓ももっと楽しくなる
ロブスターとザリガニは、見た目は似ていても分類や生息地、食べ方、文化など多くの違いがあります。それぞれの特徴や利用法を知ることで、料理の幅が広がり、食卓がより豊かになります。
混同しやすい種類や選び方、歴史的背景まで知識を深めることで、家族や友人との会話も弾みます。ぜひ本記事を参考に、ロブスターとザリガニの魅力を楽しんでみてください。
世界2位のピザ職人が手掛けたピザが自宅で味わえる!
ボリューム満点の5枚セットでピザパーティーを楽しもう。











